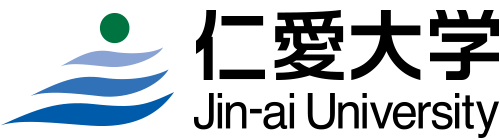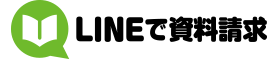-
- 戸田 有紗さん
- 健康栄養学科 2023年3月卒業福井大学教育学部附属
特別支援学校 勤務
2つの夢が叶った職場で、トラブルも経験と捉えて成長する日々!
教師をしていた叔母の影響で先生の仕事に憧れがあった一方で、糖尿病で痩せていく祖父を見て食の大切さを実感。管理栄養士として、教育現場で食育に携わることで、両方の夢を叶えることができました。管理栄養士は学校で一人なので問題の対応に悩むこともありますが、先生方が支えてくださる温かい職場です。わからないことはすぐに聞く、トラブルも経験と捉える、といった、課題を成長につなげていく向きあい方は、大学の実習で習得済み。支援学校の生徒たちの、自分にはない新鮮な視点に気づきをもらいながら、ワクワクする食の楽しさを届け続けたいです。

-
- 藤澤 真未さん
- 健康栄養学科 2013年3月卒業栄養教諭 越前市白山小学校勤務
子どもや保護者と気軽に関わることで、家庭でも食の意識を高めてほしい。
学内で作っている給食の献立を考えたり、兼務している学校も含め、5つの小中学校で食に関する指導を行っています。
毎日給食を食べている様子を見て回り、子どもたちと話をしながら味や量などの感想を直接聞けるのはやりがいがあります。子どもたちと接していると、朝ごはんを食べていなかったり偏った食生活をしていたり、あるいはマナーや姿勢の悪い子どもも目につきます。そうした課題を解決するために、おうちの人にどう話せば伝わるのか。ストレートに話をするのではなく、これから母親になる私が子育てについて教えてもらう姿勢で話しかけるなど工夫しています。
産休後も、できるだけ早く復帰してまた子どもたちの食の健康を支えたいです。そして好き嫌いない子どもを育てていきたいと思っています。

-
- 黒坂 昇汰さん
- 健康栄養学科 2022年3月卒業株式会社ほっとリハビリシステムズ 勤務
デイサービスで、いちから担ってきた栄養管理
さらには訪問栄養の開拓を目指して!
デイサービスの利用者様の食事量や回数、食欲や体重の増減など、食全般のサポートをするのが主な仕事です。ここはリハビリがメインなので、運動の基盤となる栄養はとても重要。「先生の言う通り食事に気をつけたら筋力がついたわ」といった声をいただくとめちゃくちゃ嬉しいです。また、事務的には介護報酬や介護保険制度などの専門知識も必要です。その点仁愛大学は図書館の蔵書が多く、恵まれた環境だったなと感謝しています。今、会社で目指している訪問栄養の開拓へ向けて、私も介護における栄養関係のすべてを担えるよう学び続けるつもりです。

-
- 武田 麻優さん
- 健康栄養学科 2021年3月卒業エームサービス株式会社所属福井村田製作所武生事業所 勤務
1年目で管理栄養士は自分だけ。周りの支えと自分を信じて頑張れた。
1年目は1ヵ月だけ先輩から引き継ぎがありましたが、その後管理栄養士は私一人。調理では片栗粉がダマになったり、あんが緩かったり固かったり(笑)。周りの調理師さんたちが助けてくださったのでなんとか乗り切れました。大学時代、先生が授業プリントに「あなたならもっとできる!」と励ましてくださったことがあり、「自分はもっとできるんだ」と信じて頑張れる力がついたんだと思います。人の多い職場なので、コミュニケーション力も上がりましたね。今後は食のイベントを企画するなど、管理栄養士としての役割を増やしていければと思っています。

-
- 山田 麻由さん
- 健康栄養学科 2017年3月卒業管理栄養士 食品加工研究所勤務
地域の健康増進に幅広く関わりたくて。
今は多彩な専門性に触れ、学ぶ毎日。
大学の公衆栄養学実習で、健康な人への幅広い栄養指導に興味を持ち、地域全体の健康増進に関われる公務員の道を選びました。
この研究所での仕事は、一人ひとりが担当する食品の研究課題を進めること、食品業者さんからの技術相談に対するアドバイス、細菌検査などの依頼分析の大きく3つです。実験器具の使い方など大学で学んだことはすぐに役立ちましたが、それをベースに実践的に学ぶことがとても多く、貴重な経験の連続。特に分野の違う専門職の方たちに指導していただけるのは、この職場ならでは。管理栄養士としての知識以外のこともできるだけ学ぶ努力をしています。
先輩から学ぶにも外部の方と接するにも、コミュニケーション力は本当に大事。グループワークが多かった仁愛大学で協調性が身についたと感じています。

-
- 近江 祐樹さん
- 健康栄養学科 2019年3月卒業特別養護老人ホームもみじの里 勤務
結果が出るまで時間がかかる分、粘り強さが強みになった。
卒業後、栄養士として関東で一年近く勤めましたが、実習でお世話になった当施設から管理栄養士のお誘いをいただき、地元に戻りました。でも最初の頃はパソコンとばかり向き合い、厨房には指示を出すだけ。コミュニケーションをとるため厨房に入る機会をもったことで理解が進み、今では恵まれた環境に感謝しています。大学時代は模試の成績が直前まで伸び悩んだのですが、基礎を固めれば必ず進歩すると先生に励まされ、国家試験本番で一発合格。先生のおかげで今という将来につながった、その粘り強さを大切に、より質の高い食のサポートができるよう学び続けていきます。

-
- 小林 七海さん
- 健康栄養学科 2017年3月卒業社会医療法人寿人会介護医療院 かがやき 勤務
多職種の多様な考えを受けとめ、発信する力が大切。
同じ寿人会グループの木村病院と介護医療院かがやきの間では患者さんの移動もあるため、互いに連携して栄養状態の管理を行っています。現場では、大学の知識も使い方に戸惑ったり、意外な勉強が役立ったりします。仕事を始めてからは、特に自分で勉強すること、向上心を持つことを心掛けるようになりました。急性期から介護医療まで、患者さんの生活背景にも考慮した栄養管理を行う中で、医師や看護師、リハビリスタッフなど多職種の専門的な考えを受けとめ、自らも情報共有し発信することが、より良い連携や質の高い医療・介護の提供に大切だと考えています。