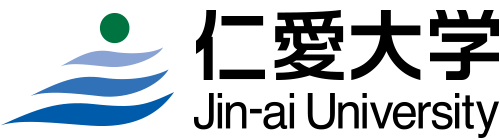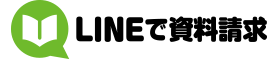人間生活学部
子ども教育学科
卒業生の声

-
- 古川 結奈さん
- 子ども教育学科 2021年3月卒業学校法人南芝原学園 ひかり幼稚園 勤務
職員全員で子どもたち全員を見るチーム保育で子どもと一緒に自分も成長!
子どもたちと先生の温かい雰囲気にひかれてこの園へ。毎月のように行事があるので、一番大変なのはその準備。歌や楽器など、大学の授業からヒントをもらうこともあります。逆に一番嬉しいのは、子どもたちが見せる「楽しい!」「またやりたい!」という笑顔や、保護者からの感謝の言葉。苦労なんて吹き飛んでしまいますね。個別に支援が必要な子どもがいたり、保護者に思いが伝わらず誤解を招いたり、日々難しいこともありますが、「チーム保育」が園のやり方。全員で問題に向きあい、先輩方の経験も自分の糧にして成長できることに感謝しています。

-
- 前澤 里奈さん
- 子ども教育学科 2018年3月卒業仁愛女子短期大学附属幼稚園 教諭
保・幼・小、すべての実習を経験して幼稚園教諭になろうと決心しました。
昔から小さい子が大好きで、将来は子どもと関わる仕事がしたいと思っていました。幼稚園の先生、保育士、教師のどれになりたいとは決められていなかったのですが、実際に実習に出てみると、就学前の子どもたちの、基礎となるところにかかわっていきたいと思うようになり、幼稚園教諭を目指すことに決めました。卒論のテーマは「ヒヤリハットの認知度を高めるためのWeb教材開発の可能性」。このテーマに決めたきっかけは、実習中の出来事。1才児クラスを見ていたとき、子ども同士の「噛みつき現場」を目撃し、そのときどう対応すればいいのか、とっさの判断ができなかったからです。ゼミの先生が情報の専門だったので、パソコンにあまり詳しくない私は、先生に一から教えてもらいながらインタラクティブ教材を制作しました。素材撮影のための園への撮影交渉や動画編集などは大変でしたが、教材を使ってくれた同じ学科の友達からは自分では気づかなかった意見が出たので、とても参考になりました。現在は2才児クラスを担当しています。子どもと一緒に遊んでいる時間が一番楽しいです。子どもそれぞれの個性や性格に合わせて対応するよう、心がけています。素晴らしい先生方に囲まれて働いているので、良いところをどんどん吸収して自分のものにしていきたいです。
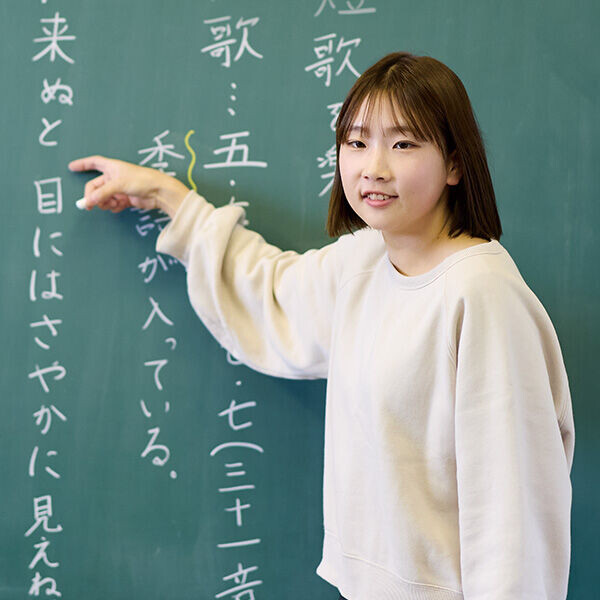
-
- 武田 亜優さん
- 子ども教育学科 2024年3月卒業福井県 公立小学校 教諭
大学4年まで迷った小学校教諭の道。
心から楽しいと思えたのは2学期からでした。
今年、着任一年目で3年生の担任になり、1学期は本当に余裕がない状態でした。でも、夏休みの初任者研修で同期の先生たちから色々な気づきを得て、2学期からはシフトチェンジ。授業の合間にちょっとゲームをしてみたり、ひとつの目標を立ててみんなで協力しあったり、児童も自分も楽しむことを目指しました。すると自然とクラスがまとまり、私も余裕ができてきて、一人ひとりの成長やかわいさがたくさん見えてくるようになったんです。夏休みは子どもも教員も多くの体験をして成長できるチャンスなのかも。今は毎日がやりがいでいっぱいです!
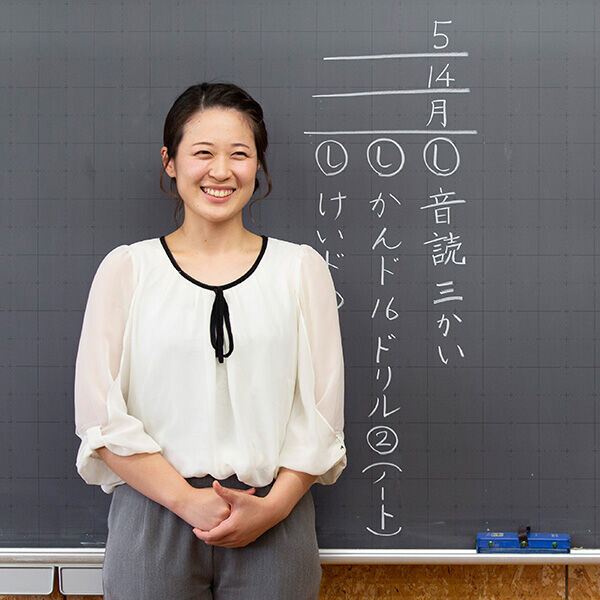
-
- 前川 聖奈さん
- 子ども教育学科 2017年3月卒業福井市小学校 教諭
子どもがより生き生きできるよう興味を引き出す授業を心がけています。
中学生の頃、友達に勉強を教えた際「分かりやすい」と言ってもらえたことをきっかけに、教員への夢を抱くようになりました。数学が好きなので、中高の数学の先生になりたいと思ったこともありましたが、数学は自分が好きだからこそ、教えるのが難しいことに気づきました。逆に苦手な国語は、なぜ分からないのか生徒の気持ちが分かることで教えやすく感じ、高校では文系を選択しました。大学在学中は、幼稚園・保育園・小学校へ実習に行きましたが、勉強を教えることのできる小学校の実習が、私にとって一番楽しかったのも、小学校教諭を選んだ理由の一つです。2年目の今は、小学2年生の担任を受け持っています。1年目よりも仕事に慣れたこともあり、笑顔の時間が増えました。子どもの成長が目に見えて分かるのがとてもうれしいです。45分間という授業時間、子どもが飽きないよう、補足のイラストをテレビ画面に映して見せたり、子どもにチョークを持たせて黒板に考えを書かせたりと、工夫しています。今後の目標は、例えば給食中に児童が牛乳をこぼした時など、すぐ先生に頼るのではなく、どう対処すればいいのか、子どもが自ら考える力をつけられるよう、指導していくことです。
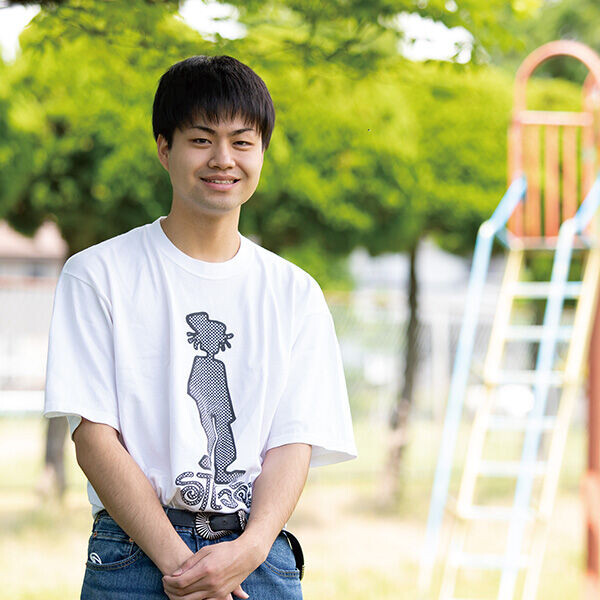
-
- 石橋 亮汰さん
- 子ども教育学科 2020年3月卒業福井市公立保育所 勤務
子どもの行動の背景や家庭支援にも目を向けていきたい。
大学時代の公立保育所での実習経験から、市との連携がしやすい公立保育所の保育士になろうと決めました。保育所以外の子ども関連の部署とも連携して、子どもに関する支援をしていきたいと考えたからです。家での様子や困りごともじっくり聞き、家庭支援にも力を入れていきたいです。そのため、保護者の方たちとも、お迎えのときなど限られた時間の中で情報共有に努めています。そして何よりも、毎日子どもと関わり、自分も成長していけることが楽しく、充実しています。声かけや遊びの流れのつくり方などを、学んでは実践し、そのたびに変化する子どもたちの反応に驚かされる毎日です。

-
- 小畑 穂花さん
- 子ども教育学科 2022年3月卒業越前市 認定こども園あわたべ 勤務
4年制大学だからこそ出来た経験。
音やリズムの楽しさを保育に活かしたい!
保育園で、いつも優しく接してくれていた担任の先生が印象的で、保育教諭になるのが夢でした。高校で進路を選ぶ時は、短大と4年制大学両方視野にあったのですが、私は4年かけてじっくり学びたいなと思い、仁愛大学に決めました。同級生と新たに吹奏楽部を立ち上げたり、勉強以外の面でも充実した大学生活になりました。私は打楽器全般を担当していたこともあり、卒業論文は「吹奏楽における打楽器の重要性」をテーマにしました。打楽器は小さな子どもでも楽しめます。研究してみてわかったことを、保育に取り入れて日常の中で音楽を楽しいと感じてもらえたらと思っています。